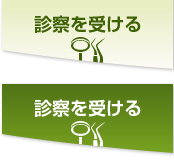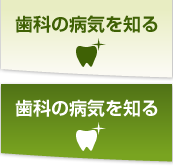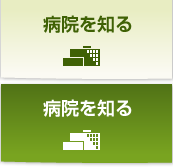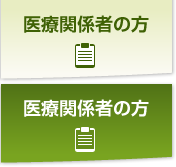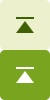うまく飲み込めない
[ 編集者:歯学部附属病院 2020年7月2日 更新 ]
うまく飲み込めない
楽しいはずの食事なのに、うまくかめない、うまく飲み込めない、といった症状があると、食べることが苦痛になることさえあります。そして、うまく食事ができない症状で、苦しんでいる方は少なくありません。
医学的は、これを嚥下障害(えんげしょうがい)といい、①食べ物を口に取り込む、②口の中で食べ物を飲み込みやすい形にする、③口からのどへ、④のどから食道へ、⑤食道から胃へ、送り込む、といった一連の動きのいずれかが障害され、食べ物をスムーズに飲み込めなくなることをいいます。
この嚥下障害(えんげしょうがい)が重度になると、食事ができなくなったり、食べ物が食道ではなく気管に入ってしまい肺炎を起こすこともあります。特に高齢者の方は、肺炎による死亡率が非常に高く、うまくかめない、うまく飲み込めないと言った症状がある場合は、専門的な治療を受けることがとても重要になります。
原因
小さな子どもから、高齢者まで、さまざまなことが原因で、嚥下障害(えんげしょうがい)の症状があらわれます。よく見られる症状は次のようなものがあります。
●食べるのが遅くなった
●やせてきた
●食べこぼす
●口の中に食べ物が残る
●のどの奥に食べ物が残る
●食事中にむせる
●咳が出る
●痰が多い
●のどがゴロゴロ鳴る
●風邪以外で熱が出ることがある
●食べ物がつかえる
●飲み込みにくい
●食べ物や胃液が逆流する
●離乳食の段階があがらない(小児)
●哺乳量が増加しない(小児)
これらの症状が見られる原因として、口やのどの手術を受けた、脳卒中後、高齢、パーキンソン病などの神経筋疾患、病気のため口から食事をとったことがない小児、発達遅滞の小児、などがあります。
検査と治療
前述した、食べるための一連の動きの中から、原因になっている箇所を検査により特定します。食べているところをレントゲン映像としてみる検査(嚥下造影検査・えんげぞうえいけんさ)や、のどの奥を直接見る内視鏡カメラ、実際に食事をしてもらい、食べているところを観察するなど、患者さんの必要に応じた検査を行います。
治療には、動きが悪くなっている箇所をサポートする装置を作製します。口からの食事が困難な方は、チューブから栄養をとることも指導します。また、安全な食べ方を身につける訓練や、かんだり、飲みこんだりする「力」の訓練、または、料理方法の工夫や食事時の姿勢などの指導をするなど、患者さんひとりひとりにあった治療や訓練を行います。
関連ページへのリンク
関連ページへのリンク